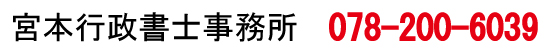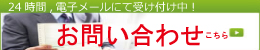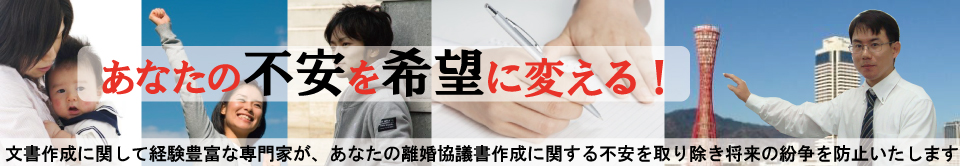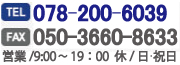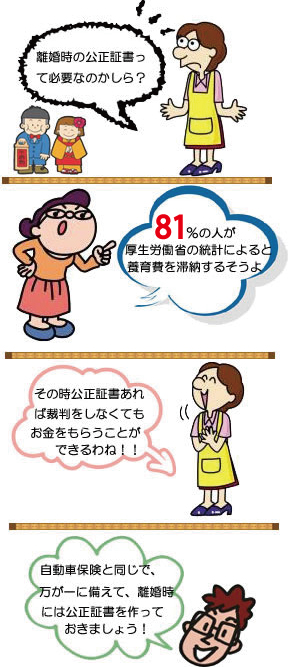親権・監護権
 離婚する際には、離婚届に
離婚する際には、離婚届に「子供を離婚後誰が世話をするのかどうかを明確にするた めに、親権者という欄」
があります。
この親権者欄に記載がなければ離婚届は市区町村役場にて受理されないようになっております。
このページでは離婚時の子供の親権を定めるに当たっての参考データを掲載しております。
もし、親権で迷われているようでしたら、このページを参考にしてみてはいかがでしょうか。
面接交渉権→
親権問題~父母の側の事情
①父母の監護に対する意欲と能力
高いほど親権・監護権者なる方が良いとされています。
EX,能力として、炊事洗濯等が挙げられます。
男性はまずは、これら基本である炊事洗濯を
覚えましょう。
②健康状態
健康なほどよいとされています。
EX、病気しがちでは、子供の面倒を
みるのには大変だからです。
←但し、親族・知人等のサポートがあれば、
健康状態が悪くともよい場合もあります。
③経済的・精神的家庭環境
豊かなほどよい。
EX、子供を育てるためにはお金が必要。
これらの条件は他方配偶者からの
養育費等で補うことができます。
④居住・教育環境
快適なほどよい。
EX、繁華街の近くの家よりも、
閑静な住宅街の方が良い。
⑤従前の監護状況
子供は父母のどちらになついていたか?
という観点から考えてみるのもよいでしょう。

⑥父母の子に対する愛情の程度
高いほどよい。
EX,自分の時間をどれぐらい費やしていたか?
⑦実家の状況
協力的であれば、上記の条件の
不備を埋めてくれる。

⑧親族・友人の援助の可能性
⑦と同様。
親権問題~子の側の事情といたしまして
①年齢・性別
年齢が小さければ小さいほど、「母性」の重要性より、母親が親権者になった方がよいとされています。

②兄弟姉妹の関係
「兄弟姉妹間は離れるべからずの原則」より、兄弟を分けて親権者を設定しない方がよいとされています。
③心身の発育状況
父母のどちらに養われている方が子供にとってプラスになるか?

④従来の環境への適応状況
子供にとって生活環境が大きく変わることは心身の発育にとって必ずしも良いとは限りません。
そのため、子供にとってできることなら、現状維持が好ましいとされています。
⑤環境の変化への適応性
新しい環境では情緒不安定になる、
若しくは喘息のような病気を持っている場合は現状維持が望ましい。
⑥子の希望など
端的に子供は父母のどちらに付きたいか?
という子供の気持ちも大切にした方がよいでしょう。
以上を総合考慮して
「親権者」を決定し、離婚届に記載された方がよいでしょう。
以上基準のみを列挙してきましたが、
具体的な基準に関しましては、
「監護の継続性の基準」に関しましては、
東京高判昭和56.5.26
特別な理由のない限り、現実に子供を養育監護している者を
優先させるべきだと判例によればなっております。
次に、兄弟姉妹がバラバラになることに関しましても、
判例は兄弟姉妹はバラバラになるべきではないとしています。
親権取得と不貞行為
離婚に際して、離婚原因(ex浮気等)を作り出した男性又は女性は
親権者として不適当であるとする判例があります。
(横浜地川崎支部昭和46年6.7)
しかし、下記の判例のように、妻が子供を連れて浮気相手の男の元にいる場合でも、不貞行為を働いているという1つの事情のみで、親権者が決まっているわけではなく、
子供にとって、父母どちらが親権を持つにふさわしいか否かで判断しております。
なお、当該事例では不貞行為を働いた母親の方に親権が渡っております。
(東京高等裁判所昭和54年3月27日)
親権・監護権の分離に関して。
親権・監護権の問題に関しては原則として、2つで1セットとなっています。
しかし、子供に関する争い(どちらが親権を取得するか否か。)が大きくなり、その争いが子供に影響してしまう場合もあります。
夫婦とも子供のためと思い、親権・監護権に関して争っているにも関わらず、子供にとって反対に悪い方向に影響してしまうことだけは防がなければなりません。
そして、夫婦間において親権に関する争いが大きくなった場合に、解決する方法が、
「親権・監護権」の分離なのです。
(根拠条文:民法766条 参考判例:大阪高等裁判所昭和36年7月14日)
では、親権者と監護権とはどのような違いがあるのでしょうか。
大雑把に申し上げますと、
親権者は子供の法律行為をサポートする者。
監護権者は、子供の生活(食事・掃除など)のサポートをしてあげる者となります。
具体的には、離婚後、父親が親権を取得し、母親が監護権を取得した場合、
母親が普段の子供の生活一般に関してサポートしており、
父親は法律的なサポート・例えば、子供の名字を変更しなければならなくなった場合の同意などが挙げられます。
もっとも、上記の具体例だけでは親権・監護権を分ける際のルール(基準)が分かりずらいと思いますので、
以下、親権者が子供に対してできること。
監護権者が子供に対してできることを記載させてもらいます。
![]() お問合せ
お問合せ![]()
親権者ができること
養子縁組契約の承諾
どのような場合に使用するか。ということですが、
例えば監護権者が再婚をし、新しい再婚相手と子供とが養子縁組をする際に、親権者は
法定代理人として承諾を行う作業を行います。
(なお、子供の年齢が15歳未満の場合だけです。)
監護権が再婚をするという事は、血のつながりはなくとも、もう1人子供に父親ができることになります。
そのような重要なライフスタイルの変化時に親権者として責任ある対応をする場合に親権と監護権とを分けるメリットがあります。
但し、嫌がらせ目的にて親権者が承諾しないような場合に使用することは言わずとも子供にとって、プラスとはなりません。
氏の変更
子供の氏の変更
子供の氏変更の承諾権者は親権者にあります。
では、どのような場合に氏の変更の際の親権者が活躍するか?
と言いますと、例えば父親が山本であり、母親の旧姓が佐藤の場合、
母親が旧姓に戻ったような場合に、子供の名字である山本という名字と母親の名字である佐藤とが別々になる場合があります。
このような場合、子供の同居上の問題として、氏を同居している監護権者にするということがあります。
このような同居中の子供の名字が婚姻中と異なるというような場合において名字を変更できる手続きが家庭裁判所にて行うことができるのですが、当該変更手続きも子供のライフスタイルが大きく変わることだと言えるため、離婚後も子供の責任を二人で持つという観点からは分けるメリットが出てまいります。
財産管理権
その他、親権者としての子供に対する作業は以下の通りとなります。
・携帯の契約・解約
・自動車やバイクなどの購入
・賃貸借契約(高校・大学などの進学に伴うもの)
・未成年者が勝手に行った契約の取消権(高額な教材費など)
*他にもありますが、日常生活にて使用されるものを挙げさせてもらいました。
次に監護権者としてできることを記載いたします。
監護権者ができること
・教育権
どのような勉強を子供にさせるかということです。
具体的には、英語やピアノなどの習い事をさせることを言います。
もちろん、子供に無理やり押し付けることができるという意味での権利ではなく、子供の成長にとって、かかせないと考え、子供と合意の上での権利という事になります。
・居所指定権
子供の住む場所を指定する権利です。
子供が小さなうちは親と同居すると思いますが、通学範囲外の学校に入った場合などには、
必然的に親と異なる住居に住むことになります。
当該住む場所などを決める権利ということになります。
なお、賃貸借契約における親としての同意は親権者が行う権利となります。
・職業許可権
子供が、アルバイトなどの職業に就く際の同意権をいいます。
子供にとって心身の発育を損なうような仕事をさせないようにするため、そして、経営者などに
騙されて働かされないようにするために、監護権者が同意するということになります。
上記のような親権と監護権を分けるメリットは子供のためになるということにあります。
「子供は一人で分けることはできないが、親の義務は分けることができる」
縁あって二人の間に産まれてきた子供ですから、離婚しようとしまいと、子供にとって良い結果となるような決め方が肝要です。
そのため、親権・監護権を分離して離婚後両父母が責任を持って子供を養う姿勢がある方のみ定められた方が良い内容となりますので、ご注意ください。
親権問題を考える
 以上長々と書いてきましたが、
以上長々と書いてきましたが、このサイトをご覧の方は、これだけは忘れておいては困ることがございます。
それは、親権は親の権利ではなく、 子供に対する義務であるということです。
自分が子供を欲しいからではなく、子供にとってどちらの親のほうが子供の成育にとっていいか否かで決めていったほうがよいと思います。
その際、親権をもらえなかった親に対しては「子供との面接」等を取り決めていかれれば良いでしょう。
国際離婚における親権問題→
戻る