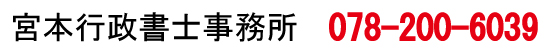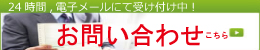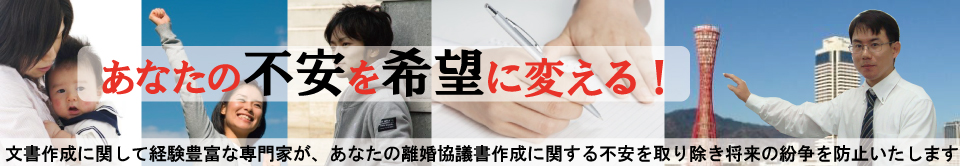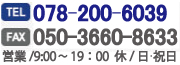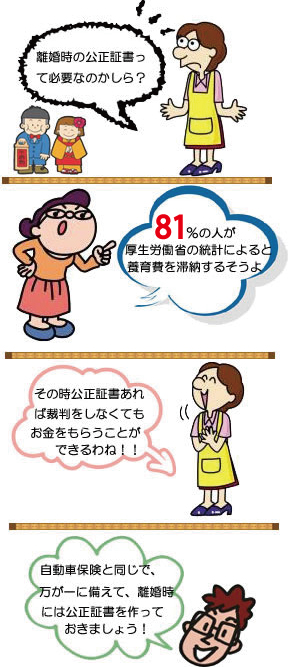保護命令
例えば家庭内暴力を受けた方が警察に
訴えたとします。
その場合に適用される法律としまして、
DV法があります。
保護命令はこのDV法
(配偶者からの暴力の防止及び被害者
の保護に関する法律)
の中にあります。
具体的には何をするか?
接近禁止命令、退去命令を例えば暴力を夫(又は妻)が
したとすればその夫に対して行うことができます。
ここで接見禁止命令とは、6ヶ月間、被害者に付きまとったり、
あるいは、住居等の付近を徘徊する事を禁止する命令です。
そして、退去命令とは、2週間、
 被害者と共に生活の本拠としている
被害者と共に生活の本拠としている住居から退去することを命じる命令です。
でもこんなことをしても夫(又は妻)が守らない恐れはあります。
しかし、もし守らなければ、1年以下の懲役、又は100万円以下の罰金を受ける恐れがあります。
仕事をしている者であれば、懲役をくらえば強制退社もありえますし、さらに前科者となってしまします。
ですから、家庭内暴力(DV)でお悩みの方は、
最寄の交番等へ相談に行かれることをお勧めします。
保護命令の条件はなんですか?
①配偶者(夫・妻)から、暴力を受けること。

・ここでいう「暴力」は身体に対する暴力に限定されます。
(DV防止法10条本文)
②配偶者(元配偶者を含む)からの、
さらなる身体に対する
暴力により、その生命又は身体に重大な
危害を受ける恐れがあること。
③子供への接見禁止命令を求める場合
→配偶者(元配偶者を含む)が幼年の子を連れ戻すと疑うに足りる
言動を行って射ることその他の事情があること。
(DV防止法10条2項)
保護命令の申し立て

①相手方の住所地を管轄する
地方裁判所
②申立人の住所又は居所を管轄する
地方裁判所
③暴力が行われた地を管轄する
地方裁判所
上記の①~③間までのいずれかで
申立てることができます。
申し立て方法
①保護命令の申立ては「書面」で申立てることが必要です。
(DV防止法12条)
*その際注意すべき点として、
申立書等は、相手方(暴力を振るった配偶者)が見たり、コピーしたりすることができます。
ですから、申立人が避難先等を秘匿している場合には、従前の住所等を申立人の住所と して記載するなどの注意が必要です。
②直近に暴力を振るわれていない場合でも、その理由によっては、保護命令を得ることも可能です。
提出資料
・申立てを裏付けるような資料が必要です。
例えば、医師の診断書、暴力後の写真等です。
いつぐらいに話し合いは行われるのか?
申立てが裁判所によって受理されると、「速やかに」行われます。
(DV防止法13条)
暴力に対するサポート機関
配偶者暴力相談支援センター
配偶者暴力相談支援センターの業務内容
①相談、婦人相談員・相談機関の紹介
②医学的、心理学的カウンセリング
③一時保護
④自立促進のため、就業の促進、住宅の
確保各種援護制度の利用についての
情報の提供助言、関係機関との
連絡調整その他の援助
⑤保護命令利用についての情報の提供、助言、関係機関への連絡
⑥居住させ保護する施設の利用についての情報の提供、助言、 関係機関との連絡調整その他の援助
(DV防止法3条3項)
![]() お問合せ
お問合せ![]()
戻る